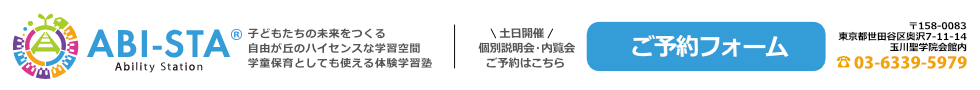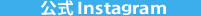|
鈴木 万久美(すずき まくみ)
アップストリーム・エデュケーション取締役ファイナンシャル・プランナー 外資系金融機関を経て全国の子供達の金融リテラシー育成を推進 |
金融教育が育む「社会を生き抜く能力」
「金融リテラシー」という言葉を聞いた事がありますでしょうか?この「金融 リテラシー」とは、金融に関する知識、感覚、能力の事を表します。文字の読 み書きが生きていく上で必要であるのと同様に、この金融に関する知識、感覚、 能力は子供達がこれからの社会を生き抜く上でとても大切になる能力です。 アメリカやヨーロッパ先進国では、小さい頃から「金融リテラシー」を身につ ける機会が沢山あり、子供達はそうした機会を通してお小遣いの管理方法や社 会の仕組み・身の回りの会社やビジネスに興味を持つことができます。それに 対し日本の子供達にとって「金融リテラシー」を身につける機会は非常に限ら れています。 自分の事や世の中の事を金融や経済・お金の側面から考えられるようになる事 は、子供達にさまざまな「気づき」を与え、主体的に物事を考えたり、取り組 むきっかけを与えます。「金融リテラシー」を子供の頃から身につけることで、 子供達は社会を賢く生き抜き、従来の常識にとらわれずに自分の人生の可能性 を広げ、充実した人生を歩んでくれるはずです。 本講座では、「金融リテラシー」を育てるために必要な 4 種類の能力「金銭感覚」 「ビジネス感覚」「投資知識」「経済知識」をバランス良く伸ばしていきます。 金融・ビジネス・投資・経済...なんて言うと難しく聞こえるかもしれませんが、 全然そんなことありません。毎回ゲームを取り入れ、お子様が楽しみながら学 べる内容になっています。楽しくて夢中になりながらお子様の「金融リテラシ ー」を育てていきます。

|
須齋 尚子(すさい なおこ)
陶芸作家 日本建築美術工芸協会会員オブジェから食器まで幅広く創作を展開 個展開催多数、公募展入賞入選等 |
土と指と〜無(ゼロ)から心を表現する
情報社会の今、溢れる情報を的確に選択し、迅速に対応処理し、最良の答、結果を導き出すことが求められています。そんな時代だからこそ、子供たちが土の持つ不思議な包容力を受け取って指を動かし、無の心でゼロから作品を創り出すという行為はとても貴重な経験ではないでしょうか?一見最短距離とは程遠いように感じる手仕事、その中の創意工夫が実は想定外の出来事に対応する際の思わぬ力の礎になるように思います。
指と脳の連動、思うようにならぬ土の扱い、創作の様々な方法論や過程を知ること、完成まで乾燥や焼成の時間を要して手元に残るカタチを成す作品となる喜び、作成時と完成時の違いに驚く等々と同時にひとつひとつの作品が貴い記憶とその年齢ならではの純粋な感性の記録、呼び起こしの宝物ともなります。半永久的である反面、割れ物であるがゆえの取り扱いを学ぶと共に自作だからこそ自然に愛しみの心も生まれます。また準備から片付けまで全てが大切だという心や作業と内容説明等の時間のメリハリや集中力、工夫して途中で諦めない力、状況に応じて協力すること等の学びも大切に考えています。そうした学びの中で、“夢中になる”ことの素晴らしさや創造(想像)の翼をひろげる豊かさを知って欲しいと願っております。
一見豊かであるように思える生活の一方でホンモノの豊かな心はどこにあるのか?どういう行為に自ずとそれが現れるのか?無意識の中にあるホンモノの心を育む一助にこの体験学習がなってくれましたら幸いです。そして、本人そのものといえる作品からその時、その年齢ならではの豊かな感性や個性を感じることは私にとりましても大きな刺激や喜びでもあります。
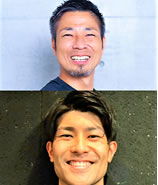
|
上野博(うえの ひろし)
株式会社GRIT NATION PERFORMANCE COACH高校保健体育教諭17年、日本スポーツ協会公認コーチ 北堀空(きたほり そら)
株式会社GRIT NATION Kidsコーチスポーツメンタルコーチ |
「本気あそび」で育てる「自信」
ABI-STAのコンセプトである、挑戦して失敗したり、仲間とうまくいったりいかなかったり、子どもたちは様々な経験から学んで成長します。このような成長の機会を子どもたちに与え続ける、に基づいて、GO WILDをミッションに掲げる我々GRIT NATION Kidsの運動神経、心身の丈夫さ、勇敢さ、コミュニケーションを育むノウハウを取り入れ、「本気あそび」というかたちで伝えています。
「本気あそび」はお題のない自由な遊びとは異なりますが、どうしたらより楽しめるかのお題に対して、子どもたちは考え、話し合い、挑戦しています。自分で決めることや対話や技に対して、失敗から学び、成功体験を積み重ねることで、自信が養われ、未知への恐怖が新しいこと、難しいことへの期待に変わっていきます。
当日のプログラム内容は子どもたちが決めるので、各アクティビティの時間配分やルール、チーム分け、役割など意見の相違があります。上級生が決断することが多いですが、下級生からも意見が出るようになり、また上級生は下級生の意見を引き出す様子も見られるようになってきました。
アクティビティの一部は、倒立前転に取り組む時間としてこちらが定めています。「できない」から「できる」へ、そして「教える」までの過程は、自分の運動能力だけでなく、共感をベースとしたコミュニケーションを育てることができます。
今では、開講前から準備をし始め、新しい遊びや難しい技へ挑戦する姿が多く見られるようになってきました。自信が磨かれ、子どもたちの成長を感じとることができます。 GRIT NATION主催のキッズイベントはこちらでご確認ください。

|
倉島 麻帆(くらしま まほ)
スマイルボイスコンサルタント フリーアナウンサー 一部上場企業をはじめ、のべ2万人以上に セミナー・研修を実施 |
心を込めて「自分」を語ろう
私達日本人はこれまで、直接的に自分の考え・気持ちを表現しないことを「おくゆかしさ」としてきました。確かにそういう一面はあります。ところで一方、「自信を持てない」若者が増えていると言われています。実際、内閣府のホームページには「日本の若者のうち、自分自身に満足している者の割合は5割弱、自分には長所があると思っている者の割合は7割弱で、いずれも諸外国と比べて日本が最も低い」との文言があります。さて原因は何でしょう。
おそらく、これまでに「自分」を等身大で語り、周囲から認められるという機会が少なかったからでしょう。それに加え、適切なトレーニングを受ける機会がなかったのも事実です。例えば、一般の教育現場での音読の指導では、主に「間違えずに読めたか否か」が重視されます。また何かの発表の場合でも、主に内容が重視されます。教育現場では自分らしさよりも正確さが求められているのが実情です。グローバル化し、様々な文化的背景を持つ人々との交流が求められる中で、もはや正確に述べるだけでは通用しません。自分の考えを心を込めて伝えるスキルが必要なのです。もちろん、自分の考えがそのまま相手に受け入れられるとは限りません。ですから、議論や交渉といったスキルも必要となります。だからこそそうしたプロセスを経て自分の考えが認められた時、自信を持つことができるのです。
本講座では、子ども達に身近な「絵本の読み聞かせ」から始め、音読、ボイストレーニング等「自身を語る表現力」を育てていきます。

|
栗田 恵子(くりた けいこ)
一般社団法人日本美術家連盟 日本画部所属特定非営利活動法人日本臨床美術協会 臨床美術士取得 |
右脳をつかって制作を楽しもう
日本が世界に誇れる伝統文化の一つに日本画があります。日本画というと多くの人は富士山や鶏などをモチーフにした絵を想像するかと思いますが、現代の日本画は、様式はありますがとても自由で様々に表現されております。 日本画のもつ繊細な色合いを幼少期に体験することはとても貴重で素晴らしいことだと思います。なぜなら、その繊細で綺麗なたくさんの色は子どもだからこそ見える力があるからです。大人になると濃紺と黒の識別が残念ながらにぶります。子どものころから色を認識して、たくさんの色の中で自分の好き色や心地よい色そうでない色など発見し、更に色の組み合わせを考えながら生活したら、どんなに豊かな感性が磨かれることでしょう。
私は、日本画を描きはじめてから20年になります。子どもが社会人になってから美術大学に入学したのは今から10年前です。その時に臨床美術を学びアートのもつ力を知りました。右脳モードで描くことは非時間的と言われており集中した楽しい時間はあっという間です。非言語的な感覚や直感も右脳を使います。左脳と右脳のバランスが良いとリラックス効果も期待できます。
卒業後は、絵のコンクール業務や放課後子ども教室勤務を経て、現在は母校で日本画の非常勤助手として学生のサポートをさせていただいております。
AB-STAでは、子どもたちが楽しく体験できて、お互いに認め合うことを大切にいたします。上手い下手は全く関係ありません。日本画の画材での色作りや様々な画材により具象、抽象、平面、立体など様々なアート体験にいたします。

|
金澤 健太(かなざわ けんた)
幼少の頃よりビートルズを聞いて育つ。ミュージシャンである父親の影響もあり、小学生でギターを手にする。その後、内海利勝(ex.キャロル)、峰厚介、Tony Maiden(ex.Rufus)、Stylisticsなど国内外問わず様々なジャンルのプレイヤーとライブを重ねる。現在は自己のバンド『Appreciation Society』をはじめ新宿KENTO'Sレギュラーバンド 『Hi jack』、コロナ禍から配信ライブを中心にスタートした神谷えりとのDuo Unit『ROOM317』など様々なジャンルの現場で活動中。 |
音楽は1人でもできますが、2人以上で演奏するとアンサンブルになります。これは言葉を使わずとも言葉以上の感情表現ができる、音楽ならではの世界共通のコミュニケーション方法です。自分の気持ちを音で表現をするということは、将来の活躍の大切な要素となる創造性に繋がるものだと考えています。そして、その音で他者との会話をする楽しみを見出せるようになれば、更に表現力が豊かになり、コミュニケーションの幅が広がります。さまざまな人とコミュニケーションが取れると、日常生活の新たな喜びが増えることを実感しています。ABI-STAの子どもたちにも、音楽を通じてコミュニケーション力を高めてもらえることを願っています。
最近の活動経歴
- 2016年GReeeeN『縁』のレコーディングメンバー
- 2017年自身初のソロアルバム『From Scratch』を発売
- 2022年自身のバンドAppreciation Societyによるアルバム『鑑賞会』を発売
- 2019年よりSing Like Talkingのツアーメンバー
- 2020年より『せたがやこどもプロジェクト日野皓正presents “Jazz for Kids”』講師

|
尾藤 江里子(びとう えりこ)
少より舞踊家の母の元でバレエ、タップダンス、フラメンコを学び、「アニー」「サウンドオブミュージック」「ピーターパン」他…多数のミュージカルや東京2大テーマパークダンサー等幅広く活躍。現在は楽曲振付やタップダンス講師として幅広い年齢層に指導する一方、また歌手「尾藤イサオ」の姪でもありTV、舞台等…数多く共演する。 中野ブラザーズ東京所属、玉川聖学院中、高等部卒業生 |
タップダンスで協調性.多様性を学ぶ
現在、小中学校ではダンスが必修になっています。自分の想いや考えを身体で表現するダンスは「心と身体を一体としてとらえる」という保健体育要網に合致し、子供達の想像・創作力やコミュニケーション能力を育む良質なプログラムとなっています。
タップダンスは音楽に合わせ、足を踏み鳴らす踊りで足の強化やリズム感・集中力を養う事が出来ます。
また群舞で踊り揃える事も多く「チームワーク」が必要となるので、他者への理解や共感を育み、協調性を学ぶことができます。それが将来の社会生活において役立つコミュニケーションスキルも身に付ける事ができます。タップダンスは極めて有意義なダンス教育プログラムなのです。ぜひ、楽しみながら未来に役立つ力を伸ばしていきましょう。

|
江間 みはる(えま みはる)
整理収納アドバイザー自ら厳選した物で生活を豊かにする提案をしている。 |
キチンとすると見えてくる
低学年の間に身につけておきたいのは「整理する能力」です。幼稚園・保育園までは、身の周りのことを始め、先生が「やってくれる」ものとして子ども達は育っています。それが小学生になった途端、自分のことは自分でやる責任感が求められます。それにフラストレーションを感じ、登校を渋るようになるのが「小1ギャップ」の原因の一つと言われています。
子ども達が「何が自分に必要で」「何をしなくちゃいけないのか」がわかっていないまま、突然「自分の事は自分でやる」ことを求められて、とまどうのは当然と言えます。 本講座は先ず、子ども達に身近な「お片付け」を、遊びを通じて学ぶことからスタートします。その後、決まりを見つけて物を仕分ける学習、優先順位をつけて取捨選択する学習、平面空間・立体空間を上手に活用する学習へと発展します。これらの学習を通じて、子ども達は自分の身の周りを整理する能力を身につけるだけでなく、将来算数の学習において必要な「およその数を把握する能力」「条件を整理する能力」「空間を構成する能力」を養います。
またポイントは、教材として「身近な具体物」を使用する事です。身近な物であるからこそ、子ども達の興味・関心を引き出すことができ、座学では得る事の出来ない、体感・実感を伴った学習になるのです。

|
黒澤 美緒(くろさわ みお)
イラストレーターグラフィックデザイナー
|
『デザイン』について、楽しく!学ぼう!
私たちの日常生活は様々な『デザイン』であふれています。スーパーやコンビニエンスストアで売られている食品のパッケージ、デパートやショッピングモールで売られている洋服やバッグ、家の中で使われている椅子や机といった家具、電車やバス、飛行機などの乗り物の形状から、ゲームやアニメに登場するキャラクターなどなど、それらの全ては誰かが『デザイン』をしたものなのです。
日常生活の中で何気なく触れているこの『デザイン』ですが、実際にどのように『デザイン』がおこなわれているか?は専門学校や大学にいくまで、なかなか触れたり学んだりする機会が与えられません。
単純に楽しく絵を描くということから、一歩踏み出して『デザイン』という視点で日常生活を眺めてみることで、社会の仕組みや、仕事という感覚が意識できるようになります。 私が教える『デザイン』はグラフィックデザインやイラストレーションです。雑誌や本の表紙や挿絵、食品や化粧品のパッケージのデザイン、広告ポスターやファッションブランドのアパレルデザインなどの仕事の経験を活かして、それらの『デザイン』の最初の扉を開くような、学びや体験をしてもらいたいと考えています。そして『デザイン』を通して、社会とのコミュニケーション力を磨いていたけたらと思います。

|
菅野 昌志(かんの まさし)
公益財団法人日本棋院棋士 プロ七段日本棋院棋士の囲碁スクール講師 小・中・高校での囲碁授業を500回以上担当 |
囲碁から学べる力は無限大
世界最強の囲碁AIを開発した、グーグルのトップAI研究者デミス・ハサビス氏は、「囲碁は世界最高峰の情報ゲーム」と表現しています。囲碁を学び効率の良さや自己学習する能力などを身に付けたAIは、その後それを応用して様々な能力に発展させ、今のAIの飛躍的な進化につながりました。
囲碁の変化の数は、宇宙の原子の数より多く、進化した囲碁AIでもまだ囲碁を解明できていません。
同じ局面は二度と現れないので、知識と記憶だけでは最善手を打ち続けることはできません。常に正確な状況判断と先を読む力、大局観と創造力を使い、正解がない中で工夫を凝らし最善を追求していきます。また、正しく判断できるよう、精神的なコントロールも必要になってきます。こうして人間も囲碁から多くのことを学び、生きていく中で必要となるさまざまな力を身に付けることができます。
このように書くと難しいもののように感じられるかもしれませんが、そんなことはありません。
今では、小学生の大会も開催されるようになり、全国から定員いっぱいの小学生が参加、七段同士の決勝戦など、小さなうちこそ囲碁が学びやすいことが知られてきました。そこで優勝したこともある仲邑菫さんは、なんと10歳0か月の時にプロ入り、最年少記録を更新しました。
囲碁のプロは年齢制限(22才まで)もあり、年間数名ずつしかプロ入りできない狭き門です。小学校低学年は囲碁を始める適齢期といえます。また、学業への効果も期待され、受験準備のために習い事に囲碁を選ばれる方も増えています。小学校から大学まで、授業にも取り入れられている囲碁を、プロにもなれる可能性のある今のうちに体験しましょう。

|
鈴木 佳都紗(すずき かづさ)
公益社団法人才能教育研究会スズキ・メソード チェロ科准指導者 リトミック研究センター ディプロマA 国立音楽大学大学院後期博士課程在籍 |
チェロを通して音楽への興味を広げる
私たちが普段何気なく耳にしている音楽。
一口に音楽と言っても様々なジャンルがありますが、『チェロ』という楽器をお耳にしたことはありますでしょうか?クラシック音楽、オーケストラなどにご興味がある方はご存知かもしれませんが、ヴァイオリンやピアノと比べるとやはりマイナーな楽器と言えます。実際に「チェロを演奏したことがある」という方はなかなか少ないかもしれません。
チェロはヴァイオリンの仲間、弦楽器に分類され、オーケストラでは主に伴奏を担当する、いわば「縁の下の力持ち」の楽器です。ヴァイオリンと同じように奏でますが、ヴァイオリンよりも大柄で、椅子に座り、楽器を後ろから包み込むようにして演奏します。その為、体に楽器の響きがダイレクトに伝わり、振動として楽器が音を出していることを体感できます。ピアノより音をきちんと出すということは難しいですが、その分いい音が出た時の感動は大きいです。また、誰がいい音を出せたかなど、音を静寂の中で聴きとるという「聴く」能力や「集中力」も身につきます。チェロを弾くというのは、非認知能力や運動神経や感覚というものと関わりが強いものなのです。
本講座では、チェロの体験を通して楽器への興味を持ってもらうこと、ひいては音楽全体に興味の幅を広げていくことを目指しております。その為、チェロの体験以外にも、音楽の基礎知識を深めるため、リトミックなどを交えて講座を行っております。
「言葉に合わせてリズムを打ってみる」、「音楽に合わせて歩く、止まる」、「音楽を表現してみる」など、実際に体験、体感することにより言葉も含めた「音」楽をより楽しく学ぶ機会としております。

|
恒見 愛里(つねみ あいり)
バルシューレC級指導者中学校教諭一種免許 高等学校教諭第一種免許 保健体育 一般社団法人日本キッズヨガ協会キッズヨガ指導者(キッズパート) |
ボール遊びで潜在能力をはぐくむ
ボール遊びは運動が苦手、運動をこれからはじめる子のスポーツの入り口です。この授業では子どもたちの自由な発想や工夫を大切にし、「好き」「得意」のきっかけを作り、小さな”できた”をたくさん経験させ、自己肯定感を育みます。また自身で考える時間やチームで話し合う時間を積極的に与えます。 授業の中心的プログラム「バルシューレ」とは「ボールスクール」(Ball school)、子どものボールゲーム教室のことで、ドイツ・ハイデルベルク大学スポーツ科学研究所で開発されました。個別種目の学習に入る前の低学年の時期に、すべての球技に共通する最大公約数的な基本要素を遊びながら身につけることができるよう工夫されており、さまざまな球技の基礎技能がオールラウンドに習得できるように作られています。また、単に走る・捕る・蹴る・投げるといった技能だけを身につけるのではなく、状況に合わせた判断力や空間把握能力を養うという特徴があります。 子どもたちはボール遊びに楽しくかかわりながらも、基礎運動能力・自発性・社会性を身につけていきます。